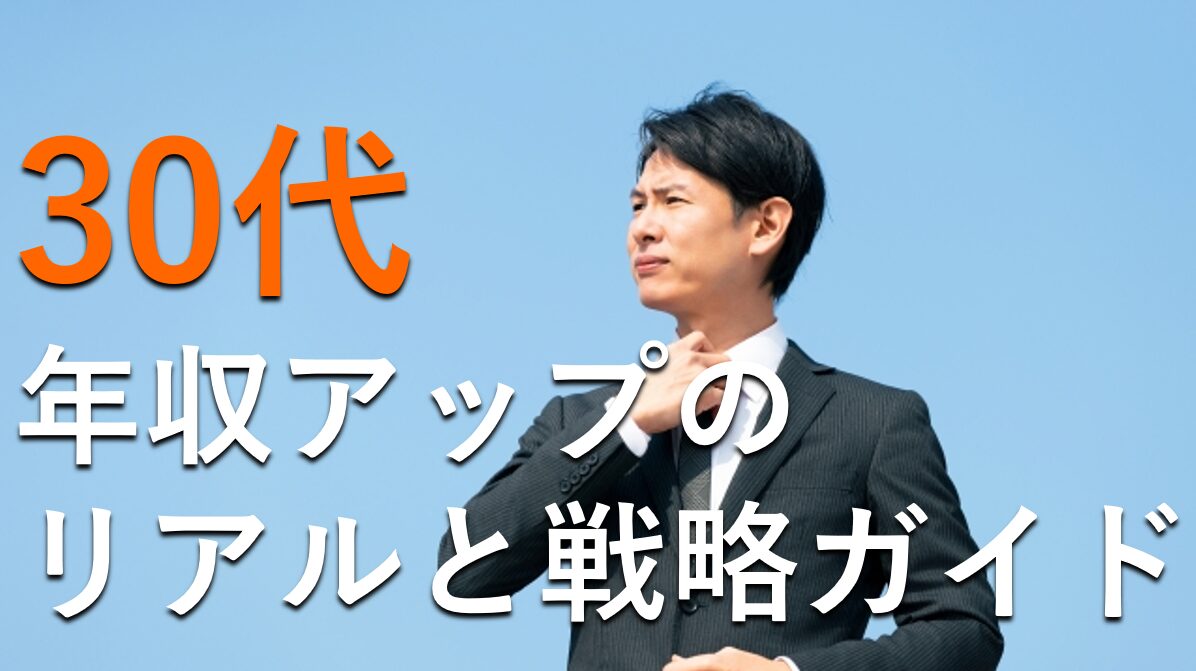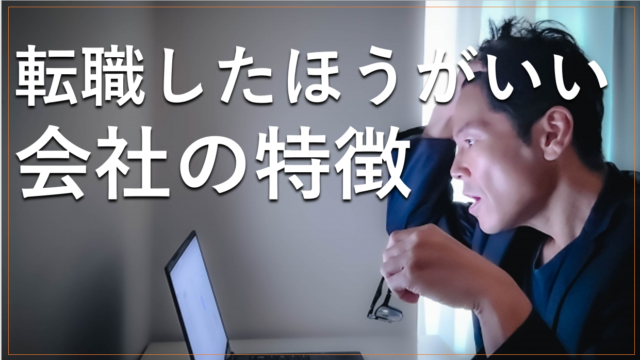30代で転職を考える際、多くの人が最も気にするのが「年収」です。「今より上がるのか」「下がるリスクはあるのか」「年収を上げるためには何をすべきか」といった不安や疑問に直面します。本記事では、30代の転職で起こりうる年収アップ・ダウンの実態やその理由、そして後悔しないための対策を解説します。
1. データで見る30代の転職と年収変化の傾向
dodaの調査によると、30代で転職した人の約6割は年収がアップしています。一方で、約2割は年収がダウンしており、決して「転職=年収アップ」ではないことが分かります。
▶︎ 主な調査データ(doda「転職成功者の年収変化」2023)
- 年収が上がった:62.4%
- 年収が変わらなかった:17.6%
- 年収が下がった:20.0%
(参照先:DODA)
年収が上がった人の多くは「スキルを活かした同業種・同職種」への転職。一方、年収が下がった人は「未経験職種への転職」「地域変更」「働き方重視」のケースが目立ちます。
2. 転職で年収がアップするケースとその理由
年収アップを実現している30代の転職者には、以下のような共通点があります。
スキル・経験を活かして“同職種・同業界”に転職
- すでに持っている専門スキルや実績を評価されやすく、即戦力として高待遇で迎えられるケースが多いです。
- 例:広告代理店から別の大手広告会社への転職/SaaS営業職から他社SaaS営業への転職
- 企業規模が大きくなる、もしくは報酬制度が優れている企業に移ることで、年収が100万円以上アップすることも。
ハイクラス・マネジメント職への昇格転職
- これまでの実績が評価され、リーダー職やマネージャー職として採用されることで、基本給+管理職手当の増加が見込まれます。
- 例:中小企業の営業チームリーダーから、大企業の営業マネージャーへ
- 年収600万円→800万円超という事例もあり、責任が増える分、年収面でも飛躍が期待できます。
成果報酬型(インセンティブ型)の業界へ移動
- 不動産営業、保険営業など、成果に応じた報酬制度が確立している業界においては、基本給に加えて成果報酬が得られるため、高収入を狙えます。
- ただし安定性には欠けるため、自身の営業力や交渉力に自信がある人に向いています。
高需要職種(ITエンジニア・データアナリストなど)へのキャリアチェンジ
- 近年、デジタル人材の需要が高まっており、未経験からの転職であっても、スキル習得とポテンシャルを重視する企業が増加しています。
- スクールやオンライン講座などで事前に学び、転職市場におけるアピール材料を用意することが年収アップの鍵です。
外資系企業やスタートアップへのチャレンジ
- 外資系企業は成果主義が強く、経験やスキルに応じた報酬を提示する傾向があり、同じ職種でも国内企業よりも高年収になることがあります。
- スタートアップでは役職や裁量の大きさに応じて年収提示が柔軟な場合があり、交渉次第で大幅アップも可能です。
このように、年収アップを成功させるには、自分の「強みを活かせるフィールド」を見極めて転職活動を行うことが鍵となります。
3. 転職で年収がダウンするケースとその理由
年収ダウンを経験する30代の転職者には、以下のような共通した背景があります。
未経験職種・異業種へのチャレンジ
- まったく異なる職種や業界に挑戦する場合、企業側は「即戦力ではない」と判断するため、初年度は見習いポジションに近い扱いとなり、年収が低く設定されがちです。
- 例:営業職から人事職への転職、事務職からエンジニア職への転職など。
地方移住やフルリモート希望による転職
- 地方に本社がある企業や、地域限定勤務のポジションは、同じ職種でも首都圏に比べて年収水準が低い傾向にあります。
- また、フルリモート勤務可能な職場は、時間的自由を得られる一方で、その代償として給与水準が抑えられることもあります。
ワークライフバランスや働きがいを重視した転職
- 年収よりも「やりがい」「家族との時間」「ストレスの少なさ」などを優先した結果、年収が下がる選択をする人もいます。
- 例:ベンチャー企業からNPO法人への転職/時短勤務を希望しての転職など。
転職回数の多さ・ブランクによるネガティブ評価
- 短期間での転職を繰り返していたり、長期のブランクがある場合、企業側から「安定性に欠ける」と見られ、条件交渉において不利になりがちです。
景気や業界のトレンドの影響
- コロナ禍や経済不況の影響で、企業の採用条件が厳しくなっているケースもあり、「以前よりも低条件でしか転職できなかった」という声もあります。
年齢による“オーバースペック”懸念
- 特に35歳を過ぎると、応募先企業から「このポジションには高すぎるスキル・経験」と見なされ、給与を抑えて採用される例も。
- ポジションに対して求職者のキャリアが過剰と見なされると、年収が相場より低くなるリスクがあります。
このように、転職での年収ダウンにはさまざまな要因が絡んでいますが、いずれも「納得して選んだかどうか」が重要な視点です。短期的な損失であっても、目的やキャリアビジョンに沿った選択であれば、中長期的にはプラスに働くことも多いのです。
4. 年収アップ・ダウンの良し悪しは“目的”次第
転職の成否は「年収が上がったか/下がったか」だけでは測れません。大切なのは、「自分は何のために転職するのか」という目的を明確にし、それに見合った選択ができたかどうかです。
年収アップは“即効性のあるメリット”だがリスクもある
年収が上がった人の多くは、スキルを活かして同職種に横スライドしているケースです。これは即戦力として評価されやすい一方で、「仕事内容は前職とあまり変わらず、新しい経験が得られにくい」という懸念もあります。結果として、キャリアの幅が広がらず、将来的に停滞する可能性もあるのです。
年収ダウンでも“長期的な投資”になりうる
一方で、年収が下がった人の中には、あえて未経験職種や成長分野に飛び込んだ人も多くいます。このような転職は、短期的には収入が下がることがありますが、「経験値を高める」「専門性を広げる」など、中長期的なキャリアの資産形成につながる可能性が高いです。
自分の“キャリア軸”を持つことが重要
「どの選択が正解か」は、他人ではなく自分自身の価値観と将来ビジョンによって変わります。転職活動においては、「今はスキル獲得を優先する時期か」「年収を上げてライフプランを安定させたいのか」など、自分なりの判断軸を持つことが、納得のいく決断につながります。
5. 年収ダウンを防ぐための転職戦略
転職における年収ダウンを避けたい人に向けて、実践的な戦略を紹介します。
職務経歴書で“定量的な成果”をアピールする
- 自分の成果や実績を、数字で示すことで企業にインパクトを与えやすくなります。
- 例:「前年比120%で売上を達成」「新規顧客開拓で年間20社を獲得」など。
企業の年収レンジを事前に調査する
- 転職会議、OpenWork、doda、エン転職などの口コミサイトや求人票を活用し、希望企業の年収相場を事前に把握しておきましょう。
年収交渉は“戦略的”に行う
- オファー面談時に「希望年収」の根拠を示すことが重要です。
- 同職種・同業界の市場平均、現在の年収、成果実績などを踏まえて主張しましょう。
年収以外の“総合報酬”にも目を向ける
- 基本給だけでなく、賞与、住宅手当、交通費、福利厚生、ストックオプションなどを含めた「総合的な報酬」で判断することも大切です。
キャリアパスを常に意識しておくこと
- 年収は単年で判断せず、「3年後・5年後にどうなっていたいか」を考えることで、今の転職が将来の飛躍につながるかどうかが見えてきます。
- 例えば、年収が一時的にダウンしても、新たな業界経験やマネジメント経験が積めるなら、それは将来の市場価値アップに直結します。
6. よくある質問(FAQ)
Q. 年収が下がるのはやはり失敗なのでしょうか?
回答: 必ずしもそうとは限りません。短期的な年収ダウンであっても、経験やスキルを得て、数年後に年収が大幅に上がることもあります。転職の目的と今後のキャリアビジョンを明確にすることが重要です。
Q. 転職前に企業の年収レンジはどう調べる?
回答: 転職会議、OpenWork、doda、エン転職などの口コミサイトや求人票を活用するのが有効です。また、エージェントに聞くのも一つの方法です。
Q. 年収アップを狙うなら、どんな職種・業界が有利?
回答: IT・SaaS・医療・コンサルなどの成長業界や、外資系・スタートアップなど成果報酬型の業界は年収が上がりやすい傾向があります。
Q. 転職時に年収交渉をしてもよいのでしょうか?
回答: 適切なタイミング(内定提示後など)であれば可能です。根拠となる実績や現在の年収を元に、冷静に交渉するのがコツです。
Q. 現職より年収が下がりそうな場合、転職すべきではない?
回答: 目的次第です。「スキルの幅を広げたい」「長期的な成長を目指したい」など明確な理由があれば、一時的な年収ダウンはむしろ“投資”と捉えることもできます。
まとめ
30代の転職は「年収」という分かりやすい指標に目が向きがちですが、大切なのは“何を得たいのか”というキャリアの目的です。
短期的な年収アップを目指すのか、中長期的な成長のための経験を取りに行くのか。その判断軸を持ったうえで行動することで、後悔のない転職が実現できます。
転職を単なる年収比較に終わらせず、自分の未来への投資と捉えて、戦略的に進めていきましょう。